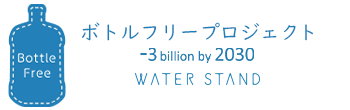社員インタビュー「使い捨てプラスチック削減に向けた日本の取組事例を世界へ」


拓殖大学大学院修士課程で国際協力学を学び、さく井技能士1級の資格を持つ朝霞営業所の古谷尚子さんにお話を伺いました。
ウォータースタンド株式会社(以下当社)に入社するまでのキャリアを聞かせて下さい。
大学を卒業後、アフリカ諸国で井戸を掘る仕事に従事していました。
2011年はエチオピアのアディスアベバに3週間、2012年はマラウィ・ムワンザに4か月、2013年はナイジェリア・ナイジャ州に3週間、2014年からはブルキナファソ・ワガドゥグ周辺6州に2年半滞在し、各国でODA(政府開発援助)による水井戸掘削工事の掘削、揚水試験、水質試験、ハンドポンプ設置の現場管理、アドミニストレーション業務、瑕疵検査業務などに従事しました。


井戸を掘り終わり、水質検査などをクリアして井戸が使えるようになると、喜んだ現地の住民から大事な家畜の鶏をプレゼントしてもらったり、女性たちがダンスを踊ってくれたりしました。
アフリカの各都市の水道事情をお聞かせ下さい。
アフリカ諸国においても、首都では各家庭まで配管が通り、家の蛇口をひねると水が出ます。
ただ、蛇口も家庭に1か所だったり、頻繁に断水したりします。

日本とはお水を取り巻く環境が大きく異なりますね。
アフリカだけでなく、私が訪れたアメリカ(ニューヨーク、インディアナ)、フランス(パリ)でも水道水を飲む習慣はないと思います。
日本では水道水が飲めますし、軟水で美味しいです。湧水が豊富にある国ですので、こんなに水に困らない環境は世界的に見てもかなり貴重だと思います。
日本に暮らす私たちは、日本の安全な水環境が貴重なものであるという事だけでも再認識すると良いと思います。
一方で、当社に入社して6か月※が経ちますが、PFASや配管の錆、建物の老朽化による貯水タンクの汚れ等を気にされてウォーターサーバーをお使いのお客様が多くいる事が分かりました。
2025年1月取材時点
それだけ日本では、水質や体に入る水の安全性に対して意識が高い方が多くいらっしゃるんだなと気が付きました。
アフリカで仕事をすることになったきっかけはどのようなものでしたか。
大学に入り、毎年アフリカを訪問している教授がいたのでそのゼミに入り、大学2年生の時に初めてアフリカの地を踏み、ケニアの難民キャンプを視察しました。
それまでアフリカは「遠い国」でまさか自分が行くとは思っていませんでした。
大学では国際開発学部、大学院では国際協力学研究科を専攻し、その中で環境問題について学びました。また、海外旅行に行った際に道や川、スラム街がゴミで汚染されているのを見て、環境問題の原因について自分なりに考察していました。
大学の専攻に至るきっかけは中学生の地理の授業で見た「アフリカの貧困」のビデオでした。同じ時代に生きているのに地球の裏側では過酷な状況下で生活している人達がいる現実を知り、自分に出来る事がないか考えさせられたのがきっかけでした。
「国際協力」や「開発支援」では、さまざまな支援の内容があると思います。井戸を掘る仕事に興味を抱かれたのはなぜですか?
学生時代、就職活動中にたまたまテレビで見た「ケニアの村で手掘り井戸を掘る」番組を見たことがきっかけです。
大学では、途上国の抱える課題に対して「現地の人に状況を聞きながら学ぶ」という一貫した教育方針の下で学びを深めていました。
井戸を掘る「さく井」は道路や橋の建設などよりも自然環境への負荷が低く、現地の人たちの生活向上に直結すると考え選択しました。


「国際協力」や「開発支援」には相反する側面があると思います。
確かに「開発支援」と「環境保全」は相反するものですが、どちらも必要です。
環境の事を考えると国や地域は発展できませんし、開発には環境破壊や環境汚染が付き物です。
どちらも良い悪いではなく、バランスを取りながら推し進めることが大変重要だと考えています。
井戸を掘るといった物理的な支援以外に、日本に暮らす私たちができることはありますか。
まずは興味を持ち、知ることだと思います。
日本国内の水事情や、周辺諸国での水環境はどうなのかを調べてみることが第一歩として良いと思います。
マリンスポーツや釣りが趣味の方でしたら、海の海洋汚染の現状を間近で見る、知ることができる為、その解決には何ができるのか少し考えてみること(興味をもつこと)が大切だと思います。
アフリカの現状と日本に暮らす私たちにできることを教えてください。
私が一番長く滞在していたブルキナファソでは、家の中はきれいでも門を出るとゴミが散乱している、ということを目の当たりにしました。
「あらゆるものに神様が宿る」と考え、自分の敷地の周囲も掃除する日本人とは考え方が大きく異なります。
家の外にゴミを放置するため、廃棄プラスチック製品がマイクロプラスチックとなり、環境中に飛散するといったこともあります。
開発には「知る哀しみ」が伴います。自分の身の丈に合わないものを知ってしまったことで、「もっと、もっと」と求めることで均衡状態を崩す可能性もあります。
環境対策で先行する日本には、発展する途上で経験した前例を共有し、これまでの対策を諸外国の学びとして提供する責務があると思います。

当社で実現したいことはありますか。
従業員全員がマイボトルを持ち、使い捨てプラスチックボトルを使用しないという意識を共有している点が当社の強みだと思います。
当社が掲げる「2030年までに日本の使い捨てプラスチックボトルを30億本減らす」というミッションを達成できれば、この成功例は世界のゴミ問題の解決の糸口になりえます。アフリカで仕事をした経験から、皆で同じ方向を向いて協力できる日本人の国民性を活かせば実現できるのではないかと強く期待しています。
使用済みのプラスチックボトルは土に還らないため、リサイクルやゴミ処理場がない国では川や海に流れ環境破壊、水質汚染に繋がっています。「ゴミのもとになるプラスチックを使用しない」という当社のアプローチは、諸外国が抱える問題解決のヒントになる可能性があります。
マクロの視点で環境問題を考えた時に、気候変動や温暖化を緩和させるには、政策よりも個人の意識改革が必要だと考えています。
プラスチックごみの問題は、地球全体の包括的な課題で日本だけが取り組んでいても変わらないのです。
今はSNSで世界と繋がれ、YouTubeでは世界中の動画を見ることができ、個人レベルでも発信することができます。
個人や会社の取り組みを世界に発信しながら環境問題に関心を持ってもらうこと、そして自分事で考え行動に起こせる人が一人でも増え、行動の連鎖を拡大する事が大事だと考えます。
ステークホルダーの皆様へメッセージをお願いします。
今や危機的な問題となっている温暖化と気候変動。これらの解決には個人レベルの意識改革が必要です。ステークホルダーの皆様による情報発信も必要となります。
まずは、プラスチックボトルを大量に消費し、大量に廃棄することがどういう問題につながり、どのような影響があるのかを見える化し行動変容につなげていきたいです。
マイボトルへの給水は心理的負荷も小さく、起こしやすいアクションですので、お水はマイボトルで持ち歩く文化を一緒に作っていけたらと思います。
私自身もまだまだ勉強不足ですので、企業様の取り組み等もお伺いしながらお互いに情報交換出来たら良いなと思います。
日本を起点に、みんなでいい未来をつくり出せたら良いなと思います!